2025年6月後半に面白かった病院経営ポストまとめ記事を書きました!
厚労省の各部会きっかけで、診療報酬の話題などもちらほら出始めてきていますね。
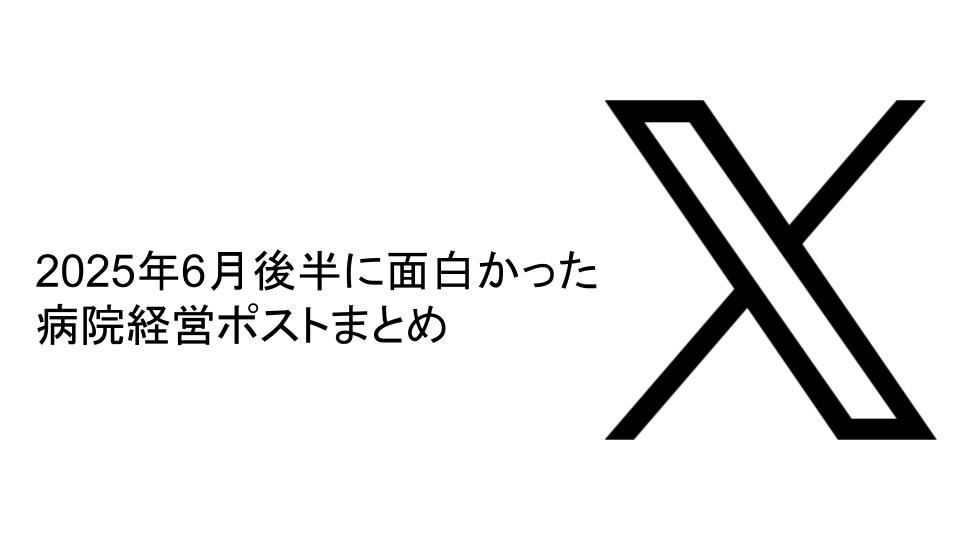
病院経営のヒント
10年前の人件費2倍突っ込んで医業収益1.5倍にしたンゴ😊
— 病院のおじかちょー (@rinsakamo) 2025年6月14日
なお新築の減価償却費と超ベア+賞与と物価高騰により利益はあまり変わらないか減る模様🥹
これがリアル病院経営なんですよね……先行オールインで勝負して『勝つしかない』ビビったら負けの世界😇 https://t.co/AVC7nIEr6Z
病院経営の厳しさを実感するためのリアルシミュレーションゲームを作ってみる。
— 宮内サトシ@医療DX💊メディアの人 (@yun__yun) 2025年6月14日
イメージこういう感じ。
今月の収支が1520万の赤字で、
「至急:3ヶ月連続の赤字です。資金ショートの危険性があります」
「注意:内科の常勤医が1名、退職を検討しています」
は胃がキリキリする…。 pic.twitter.com/7PrLHSsBn2
私が見てきた経営破綻した病院の8割に共通していたのが、
— 中田賢一郎/医師x僧侶x経営者/病院再生 (@n_kata) 2025年6月20日
「本当の数字を誰も見ていなかった」ということ。
✔稼働率の水増し
✔実態と合わない収支予測
✔赤字部門を“聖域”扱い
私は買収時、まず“嘘のない現実”を見ることから始める。
経営も医療と同じで、…
臨床に人生を捧げた幹部医師に敬意はある。
— 田中 (@2357yu) 2025年6月17日
ただ今、病院に本当に必要なのは『経営を学ぶ医療人』ではなく、『経営と現場の双方に責任を持てる意思決定者』なのよ。
経済成長と人口増を前提にした“ふわふわ医療制度”から、価値と成果前提にした“ばちばち医療制度”への変化に脳がついてこれるのか…?
大学病院で特有の話…になってしまうかもしれませんが、文部科学省のサイトに「藤田医科大学病院」と「佐賀大学医学部附属病院」の経営改善の取組が紹介されています。
— 診療情報管理士のノブ(フェイク) (@HIMnobu) 2025年6月25日
どの病院もやろうと思ってもできていないことがしっかり実践されている印象。
「経営合理性のための医療DX」というフレーズは秀逸。 pic.twitter.com/BXYYnKUqT7
これは半分負け惜しみなんですが、今のルールだと高齢者が多い地区の地域救急や高齢者施設の後方支援をちゃんとやってるとDPCの係数全然上がらないんで、スペシフィックな急性期医療の収益の足をめちゃくちゃ引っ張るんですよね。次の改定でもこの評価体系が維持されるならDPC離脱する病院増えそう。
— 藤田哲朗@富山の医療経営士・中小企業診断士 (@tetsurofujita) 2025年6月16日
5~6月に入院患者が減る理由について、いつまでも農繁期が理由じゃないでしょう。
— K Mat (@KMat74562541) 2025年6月22日
過去は農繁期だったから患者が減る→患者減るからその時期に学会やれば良い
だったのが
学会が集中するから患者が減るに、変わったんじゃないんですか?
疑似相関から直接的な因果関係に変わったんだと思いますけど。
病院経営はとても厳しい時代だ
— ぱろすけ (@parosuke1976) 2025年6月20日
やることをやってダメなのか?
ほとんどやらずしてダメなのか?
前者なら諦めはつく
課題に対して打ち手を考える
ステークホルダーを動かす
実行 & フィードバック
まだ出来ることがあると思うの
優れたサービスを提供する場合のインセンティブがないんですよね。
— Takahiro_Inukai@病院DXと医療機器開発支援 (@Takahiro_Inukai) 2025年6月16日
保険診療制度は「当該制度だけで完全かつ最高の医療が提供されること」だから、自費との兼ね合いがすごく難しい。
差額ベッド代にしても無償病床を確保し、かつ患者が無償を希望すればお金取れないですしね。 https://t.co/fHsHNJGblb
現場のカイゼン
DXをIT化、デジタル化みたいな風に捉えられがちだけど、実際デジタルに切り替わった上で起こる変化や溜まる材料などを踏まえどうそのアクションと周りに変革を起こすか。そういう意味では本当の意味でのDX化されているものは限られている気がする。(完全にこれ某偉大な大先輩の受け売りですが)
— Koichi_Tero | HMW(平成医療福祉グループ) (@kakkoiiyowamusi) 2025年6月18日
FAXは「情報の伝達」と「紙の出力」を同時に行うデバイスなので、受信者のオペレーションが紙媒体を前提にしているうちは利便性が高い。ここがペーパーレスにならないとFAXから卒業できないし、するメリットもない。しかも医療機関はHIS系が閉鎖されてるので、情報を紙出力しがち。
— 藤田哲朗@富山の医療経営士・中小企業診断士 (@tetsurofujita) 2025年5月2日
一人勝手に全病棟から外来まで院内ラウンドを始めて5年🏥職員の人や患者さんに挨拶しながら掲示物や汚れなどを見ることを心掛けてます。前は経営幹部で集まって討議しながらラウンドしてた過去が懐かしい。やっぱり少しでもフットワーク良くしておくと頼ってくれるから🐱嬉しい、
— ぼやきリーダー (@him_iryoujimu) 2025年6月7日
これは医事界隈の部署仕事にも言えて、崩壊寸前の部署は「チームを助ける強度」がほぼゼロになっていることが多い。
— 難波津の蟹 (@RideRead) 2025年6月14日
ただ「じゃあ皆で助け合いましょう」と単に言うだけで復活するものでもないので、まずはマネージャーが率先する必要があるけど、これをやりたがらないマネージャーが多いのよねぇ。 https://t.co/NaAfSXhASH
日本語話せない外国人の初診は、これから翻訳料を取ることにした。
— 都心のツブクリ雇われ院長 (@448ymmt) 2025年6月25日
うちの事務は仕事はそんなにできないが、案外イイ奴なので、外人の問診とか、丁寧に一個ずつカタコトの英語で聞いてやっている。
そういう努力は翻訳料としてコストに単価に転嫁させねば、ただのお人好しになってしまう。
医療ソーシャルワーカーが転院支援をする際、病院の選択肢が多過ぎるとクライエントは迷って決断すること自体をやめてしまう。
— Kei@社会福祉士 (@kei5850) 2025年6月17日
選択肢を絞り、比較ポイントを明確に伝えることで、スムーズな意思決定を支える。 pic.twitter.com/VK7RII3Yxk
診療報酬の算定
電カルに記載してたら「その加算取れる」のであって、診療行為やってても「電カル(診療録)に記載なし」なら取れないわけですよ。
— 艦これ@永遠の備蓄戦士 (@hiyori_t) 2025年6月20日
やった事をきちんと記載しているかで加算が取れるのでいい加減な診療録記載だと逆に厚生局から「加算取りたいなら施設基準きちんとやれよ」ってガチお説教されます>RT
電カルを管理する側もこれを意識していない人が多い。
— 院内SEのぼやき (@HI_technologist) 2025年6月23日
「〜加算」「〜情報提供料」「〜指導料」など行為としてオーダー登録できるようしてくれと依頼はあるけど、その根拠を証明できるかも確認が必要だと思う。
監査の時に慌てることがないように。 https://t.co/Ft0JaABBEB
別病院の院内SEや同僚に診療報酬改定の話をしても「うち(情報システム部)はあまり関係ないんで」って言われるけど、最悪こうなること予測してないんだろうなぁ。
— 院内SEのぼやき (@HI_technologist) 2025年6月24日
言われたことしかしてないんかな。
私が尊敬してた先輩は改定の度に資料を一通りチェックしてシステム絡むところをマーキングしてた。 https://t.co/pxTtMV6AQw
施設基準上、失ってはならない人材がまた1人長期離脱に。施設基準管理システムを導入しておけばこういう時でも慌てず対応できるのだろうか。(直接的にどの加算等に影響してくるか、その加算を失った時どの程度影響があるのか、間接的に他の加算に影響しないか等)
— ぴらりん@医療DX (@pirarinJP) 2025年6月30日
2026年度改定に向けた議論
地域包括医療病棟と地ケアの患者像が同じなのは当たり前。
— K Mat (@KMat74562541) 2025年6月18日
今はどこから来てどこへ帰るかが設計上違うだけ。
地域包括医療病棟は在支病、地ケアは看護職員配置加算で相互の領域をカバーできるけど、地域包括医療病棟は、在院日数縛りのせいで退院調整時間が余計に必要な地ケア領域のカバーはキツい。
いまだ訪問診療は贅沢!医者の金稼ぎの手段だという声が聞こえるけど、通院困難⇒入院の世界線の方が医療費はかさむよね
— ざいたくいのぐち (@grumblehomecare) 2025年6月18日
入院>在宅>外来の順にお金はかかるので要は適応の問題
もう施設メイン・軽症者在宅はかなり診療報酬削られているし
むしろ紆余曲折を経て割と適正化されてると思うんだけどにゃ
これが現時点での政策の考え方で完全に正しい理解だと思います。
— Hiro_ProDoctors (@Hiro_MD_MBA) 2025年6月18日
だからこそ、私は在宅の次は、外来だと思ってます。
在宅推し後の10年は、介護タクシー、モビリティ、オンライン診療のようなサービスが来る。 https://t.co/Rss73THpPF
AI活用・IT化
生成AIを退院サマリー作成に利用する取り組みはあるが診療情報提供書を書かせる取り組みにはなかなか普及しないあたり、AIが出してくる文章のクオリティがわりとアレなのではないかという疑念を持つ(退院サマリーと違って診療情報提供書は読み手がいるからなぁ…)https://t.co/wGOE3UM4k9
— レ点🧬💉💊 (@m0370) 2025年6月14日
最近DXで驚いた事例は技師2名の手作りコマンドセンターを活用し経営改善に繋げた件である…
— Anad A 🕳 (@syu5o) 2025年6月14日
成功要因の自分の理解として
①内製した手触り感や院内業務や情報フローの見直し
②ケアミックス病院の規模感
③当該職員という人的資産
があると考える。恐らくBIツールだけ置いても同じ成果は難しいはず🏥
最近痛烈に必要性を感じているのがオーダーとカルテ記載内容から加算や管理料の算定漏れをサジェストしてくれる機能。そろそろAIでなんとかならんか。
— 藤田哲朗@富山の医療経営士・中小企業診断士 (@tetsurofujita) 2025年6月23日
特に救急医療管理加算。「細胞外液1,000mL+当日食事なし」とか「予定外入院後48時間以内の手術」とかで拾って『症状詳記してください』ってポップ。 https://t.co/zvNKeQ33jQ
GoogleドライブはGeminiが自動で要約画面を表示してくれるように。
— 長(おさ)英一郎 医療経営&DX化推進 (@eiichiro49) 2025年6月27日
Google Workspaceを導入する病院が増えてきていますが、このように厚労省資料を自動で要約してくれます。 pic.twitter.com/jFlKm9IX3F
人材育成・マネジメント
病院を黒字にするより、
— 中田賢一郎/医師x僧侶x経営者/病院再生 (@n_kata) 2025年6月27日
「いい職員が辞めないようにする」方がはるかに難しい。
黒字にすればするほど職員が辞める病院もあります。
“数字”より“空気”が壊れているところは、
医療法人としての寿命が短い。
ミドルマネジャーの一般的な苦悩は、企業の評価制度や教育制度の整備によりかなり軽減できるのではないかと感じた。
— Y.MURAYAMA,OT,MMgt (@otmuracha) 2025年6月22日
育成の仕方。面談の進め方。フィードバックの仕方。上長の役割。自己啓発の方向性。モラルブレーカーやモチベーションブレーカーへの対応などなど。
あくまで可能性として。
市役所への出向がないプロパーを増やすのは理解できる。しかし採用した後の教育は育成計画もないし研修は行政向けの内容だし、将来的に病院を支えてくれるプロパーを増やすというのは口先だけで、今の業務が回ればいいとしか考えられてないんだろうなぁ。 https://t.co/dBQCMmAsRp
— sakudore (@HIM_dressing) 2025年6月15日
年に一度の各部門長との個別MTG📝
— Dr中々|病院再建奮闘医(元外科医) (@DrNakanaka) 2025年6月28日
1年間の業績をねぎらい
これからの期待値を直接伝える絶好の機会
管理者としてのビジョンや想いを
熱く、クールに、そして最後は同席者を巻き込み
笑いで締める😆
自分なりの面談スタイル😎#病院管理者の苦悩
【有能なスタッフほど早期退職しがち②】
— Dr中々|病院再建奮闘医(元外科医) (@DrNakanaka) 2025年6月20日
責任感が強い人ほど、問題を棚上げされた状況を許容できません。一方で組織への愛着(育てられた恩や周囲への謝意)があるほど退職へのハードルが上がります。…
学会関連
昨日の医療政策学会、すごくいいなと思ったのが、ポスター会場にポストイットが置いてあって、ポスターにコメント残せるスタイル。これはモチベーションあがるよい仕掛け😊わりと一般的なんですかね、、今まで参加した学会では見たことなかったので感動でした✨ pic.twitter.com/K1KIKDDZI0
— 稲葉可奈子🐾産婦人科医『シン・働き方』 (@kana_in_a_bar) 2025年6月29日
そういえば「何の学会がお勧め?」
— ささがさん (@sasaga012) 2025年6月29日
というのがあって軽く答えたんだけども
ちょっと需要あるかも?
・日本医療マネジメント学会(https://t.co/ns1OBvByGz)
経営層、事務、看護師、システムなど幅広く
知識が入ってくる。学術総会は普段聞けない話も
聞けるのでお勧め。https://t.co/PbLvLCNFct
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いかがでしたでしょうか?
あっという間に2025年も半年が終わり、折り返し地点を過ぎて暑い夏がやってきますね。
体調に日々気を付けて、夏季休暇はきちんと取りつつ、頑張っていきましょう!